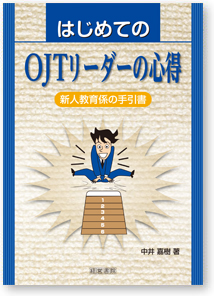|
立ち読み
|
本書は、はじめて部下をもった若手社員に向けて、豊富なイラストや図解を交えて、いかに部下を育成し、組織力を高めていくか、を伝える内容となっています。すでに管理者として活躍中の方にとっても、部下育成についての新たな視点を得られる内容です。10年来、ご好評いただいてきた「はじめての部下指導の心得」に近年の働き方の多様化などにも対応した改訂版となります。
各章に設けられた5つのテーマごとにポイントとなるメッセージを掲載し、各章の最後には管理者としてひと皮むけるためのcolumnを掲載しており、管理者のあり方を理解し、実践に結びつけることができる構成になっています。
経営環境が日々、加速度的に変化していくなか、どのように部下を指導育成し、企業の持てる資源を最大限に組織力として生かしていけばよいのか。部下育成に悩む会社員の方はもちろんのこと、社員研修等でのご利用にもお勧めの一冊です。
■中井 嘉樹・著
■A5判/140頁
■税込価格 1,540円
■ISBN 978-4-86326-362-8 C2034
■発行日 2023年7月6日
|
目次
- 第1章 管理者としての「仕事観」を養う
- 第2章 組織力を効果的に活かすコミュニケーションスキルを高める
- 第3章 メンバー一人ひとりを自発的に行動させるモチベーションアップ力を高める
- 第4章 部下を育て、そして自らも成長する
- 第5章 「部下タイプ別指導法」を使いこなし、実践力をつける
- 第6章 強固な負けないチームをつくる
- 第7章 キャリアビジョンを描き、実現する
著者紹介
■中井 嘉樹(なかい よしき)・・・株式会社フェアウィンド 代表取締役。中小企業診断士。同志社大学卒業後、㈱内田洋行、㈱キーエンスを経て、㈱日本ブレーンセンター(現 エン・ジャパン㈱)にてチーフコンサルタント、取締役を務めた後、現職。著書に、「はじめてのOJTリーダーの心得」(経営書院)、「新入社員基礎講座」(共著 経営書院)、「自分で売るな!部下に売らせろ!」(PHP研究所)、「会社を変える!40歳の仕事力」(共著 PHP研究所)など多数。
関連書籍
ご購入はこちら