インタビュー
「雑誌 × web」クロスインタビュー

Interview 5
〜淑徳大学 経営学部教授 斎藤智文〜
- Episode 1 日本の人事の歴史と一緒に
- Episode 2 何百人、何千人も話を聞いた結果は、「従業員中心の会社こそがいい会社」
- Episode 3 信頼関係の無い会社は、働きがいのある会社にはならない
Episode2
GPTWの広がりとミルトン・モスコウイッツの功績

編集部
でも正直、日本の人事の世界で「働きがい」って言葉が浸透してきたのは、最近ですよね。当時はどんな活動をされていたんですか?
斎藤氏
まさしく啓蒙活動ですね。講演をしたり、寄稿したり。GPTWを日本で最初に紹介した記事は「労政時報」でした。
(2005年7月22日号(第3658号)『米国にみるGreat Place to Workの活動と日本での必要性』)
当時、グループ会社の日本能率協会マネジメントセンターで「人材教育」という雑誌を出していたのですがが、そこでGPTWの大特集を組んでもらったこともありました。また、日本における「働きがいのある会社」のランキングを、2007年2月に「日経ビジネス」に交渉して載せてもらったのですけど、これまた苦労しました。興味を持ってくれた担当記者が編集長を頑張って口説いてくれて実現しました。
「日経ビジネス」は内部のライターが書くことが多いので、外部の人が執筆するのは珍しいケースなのですが、GPTWとは何かを紹介するために、2006年6月に寄稿させてもらいました。
(2006年6月5日号掲載『「働きがい」が競争力を決める』)。
編集部
ご自分で書かれたんですか? そういえば弊社で最初に登場いただいたのも、働きがいに関する連載の執筆でしたね。
(『企業と人材』2008年8/5・20号~2009年7/20号「働きがいのある会社に共通する企業文化を探る」)
斎藤氏
でもなかなか広がらなかったんじゃないかと思っていて、正直今もそこまで広がっている感じはしないんですよね。もちろん結果は結果として受け止めているんだけど、GPTWが広まっているアメリカや諸外国との違いはなんなんだろうなと、いまだに考えることがあります。
とはいえ、アメリカはそれなりに背景事情があったってことが、今回の寄稿の直前にわかったんです。
寄稿でも書きましたが、GPTWを立ち上げるロバート・レベリングは、先輩ジャーナリストのミルトン・モスコウイッツと一緒に活動するんですが、モスコウイッツはそれ以前から活躍していていろいろな提言を出しているのです。
クリントン政権のときに、ロバート・ライシュ労働長官やマーチン・マンリー次官補が「Office of American Workplace(米国職場局)」というのを立ち上げるのですが、これはモスコウイッツの助言によるものであったとマンリーが「フォーチュン」誌のモスコウィッツへの追悼文で明言してるんです。
この米国職場局は、93年から97年まで存在し、97年に無くなるのですが、すぐあと98年からフォーチュン誌に「100 Best Companies to Work for」(「働きがいのある会社100選」)という特集記事が載ることになりました。これが今も続いていまして。2023年で26年目のベスト100社の発表になりました。すごい歴史です。
要するに、米国職場局はよい取り組みだったけど十分じゃなくて、違うやり方の方が「よい職場」(「働きがいのある会社」)というものが普及するんじゃないかということで、フォーチュンの力を借りようと思ったんじゃないでしょうか。フォーチュンって、日本人が考えている以上に影響力のある雑誌で、15年前の当時で300万人ぐらいの読者がいたのです。
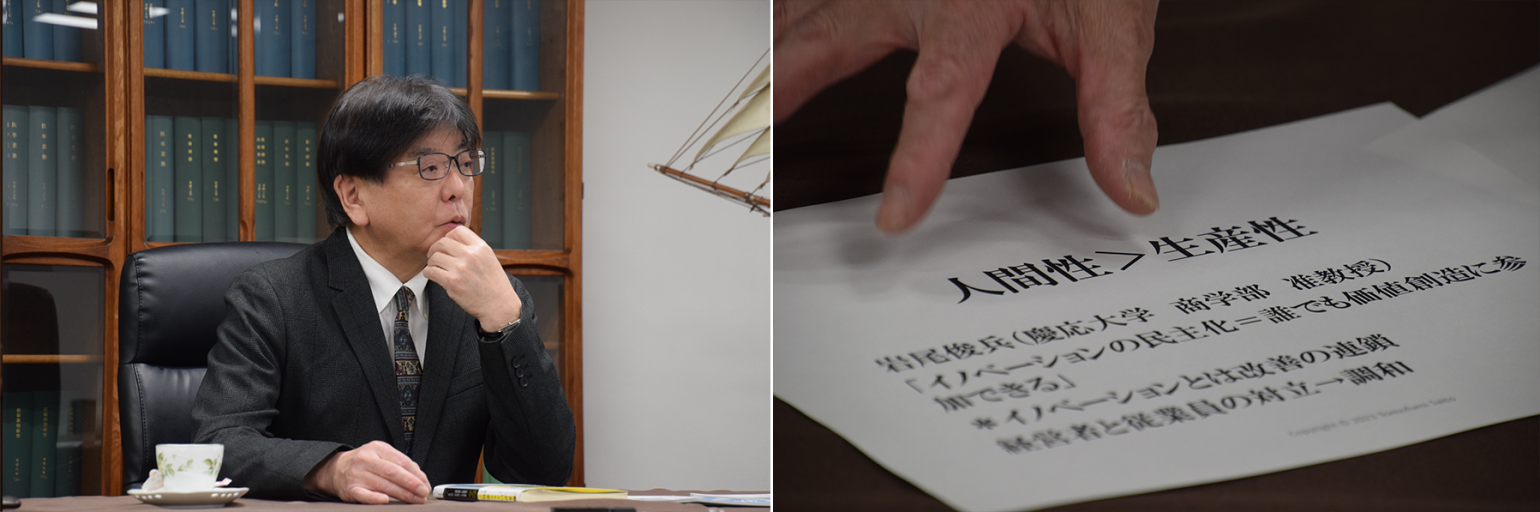
何百人、何千人も話を聞いた結果は、
「従業員中心の会社こそがいい会社」
編集部
モスコウイッツの話が出たところで、寄稿の内容に触れていきたいと思います。改めて整理すると、今回の寄稿のご依頼は、『働きがいのある会社とは何か』が出版されるということがきっかけでした。
私は当初「正直日本ではまだまだこんな状況だよね、頑張らなきゃいけない」という感じの原稿が来ると思っていたんですね。もちろんそういうお話も入っているんですが、いきなりモスコウイッツという人物の話が出てきて、ある意味びっくりしたんですよね。
さらに読み進めたら、もうこの人がいないと確かに歴史が始まってないよっていう感じで。
斎藤氏
そうでしょう?(笑) 実は昨年11月に、日本経営倫理学会のプログラムに参加しましたが、モスコウイッツについて聞いてみると、皆さんに「知らない」って言われたんです。そこで、何人かの人に「アメリカではESGの元祖と言われていて……」という話をしていたら、『働きがいのある会社とは何か』の訳者の中心になってくれた一伊藤健市先生に、「斎藤さん、この話はどこかで書かないと駄目だよ、これは斎藤さんの義務だよ」って言われたんです。そんな時にこの寄稿のお話をいただいたので、もうモスコウイッツについて書くしかないなと(笑)。
※伊藤健市
経営学者。関西大学名誉教授。大阪産業大学、関西大学を経て現職。
モスコウイッツもレベリングもキャリアが長いので、これまでにいろいろな主張を展開してきたのですが、GPTWにつながる話としては、経営学者とか経営学というものが間違っていたんじゃないかという疑念を持っていたことです。フレデリック・テイラーやピーター・ドラッカーを批判的に書いているんだけど、これは説得力のある批判で、彼らからすると要するに「従業員が起点」になっている経営書がどこにもない無い、なぜなのか、と言っているのです。
いろんな会社を訪ねて何百人の経営者、何千人もの従業員の話を聞いた結果、従業員中心の会社こそがいい会社だってことが、自分の経験上わかっているんだけど、経営に関する本のどれを見てもそういうふうには書いてないぞ、ということです。
フレデリック・テイラーは科学的管理法の父と言われていて、実際日本でも1910年代から相当参考にされ研究されたのですが、結果として、その後の経営学というか組織論は、イコール管理論になってしまったと思います。
例えば生産管理論、品質管理論、情報管理論に人的資源管理論……もう何でも管理論、つまり何かを上の者が何かを管理する研究ばっかりやってきたから、人も管理されるものになってしまいました。従業員を完全に下に見てるわけですね。
テイラーなんて完全にがっちり管理する側に回って論じていますし。もちろんその理論自体は悪いものじゃなくて、当時はそっちの方がうまく回る理論ではあったと思うのですが。
編集部
確かにテイラーは著書を読んでいると、組織というかシステムをしっかり組み上げるとか積み立てるみたいな行動が大好きな感じはします(笑)。
斎藤氏
(笑)。エルトン・メイヨーもそうだし、ドラッカーも「しっかり従業員を管理するためにプロフェッショナルマネジャーが必要なんだ」って言い方をしているんですよ。だから、やっぱり管理する対象としての従業員なんですよね。
そういえば、東京大学で史上初めて経営学の博士号を取った岩尾俊兵氏は、「イノベーションの民主化」って言葉を使っています。
すべての人が経営人材、経営人材候補で、要はいろんな人が付加価値創造できるような組織にしないといけないと言っている。主役は全員であるべきだという話で、これって言葉は違うけど、さっきの「従業員が起点」と同じようなことですね。
※岩尾俊兵
慶応義塾大学商学部准教授。明治学院大学経済学部専任講師、東京大学大学院情報理工学系研究科客員研究員、慶應義塾大学商学部専任講師を経て現職。
編集部
言われてみれば、仮に全員がイノベーション人材=主役として活躍するなら従業員が自然に前に来ますよね。最も労使関係が、どうしてもついて回るでしょうけれど。
斎藤氏
その部分で話をすると、よく経営や管理者層と従業員の対立って言い方をするけど、私は日本の場合は対立じゃなくて「分断」だと思うんです。経営者は従業員を大事にするって言うし、実際に大事にしているとしても、もう目線としてはあくまで下に見てるわけですよ。
だからそこで分断されている。よく日本の会社は一致団結なんていうんだけど、全然団結しない。そりゃそうですよ、分断されているんだから。
日本の場合さらに悪いのは、正社員と非正規社員がいるじゃないですか。非正規社員は全雇用者の40%近い数字です。これも分断です。社員食堂に非正規社員が入れない会社もあるわけで、一致団結どころの話じゃないし、イノベーションの民主化どころの話じゃない。
Work Smarter、もっと賢く効率よく働こうっていうのはいいんだけど、やっぱりWork Together、一緒にみんなで協力して働かないと競争に勝てない。だから従業員を大事にして従業員主体で進めていって、管理じゃなくて従業員を完全に主体にしちゃうような経営をすべきなんじゃないかな。これはもうアメリカでは結果として出ているんです。
編集部
あ! GPTWのランキングですか?
斎藤氏
そうです。アメリカでは「フォーチュン」でのランキング発表が始まってからすでに四半世紀以上経ってるから、GPTWモデルに関する研究論文もかなりの数になっています。実際、毎年ランキングが発表されるわけで、しかもフォーチュンのウェブサイトでは、各社の詳細の定性・定量データが公開されていますので、研究者にとっては、とても調べやすいテーマです。
ある研究では、同じ業界の中で圧倒的に業績の伸びが高い企業とランキングがかなりマッチしていた。さらに、株価が高い会社が、GPTWが発表するランキングと重なっていたのです。
ベスト100に選ばれた企業って株価がすごく伸びていて、アメリカの会社の経営者は株価が上がるのを喜ぶので、これが一番インパクトあったみたいですね。「そうか、従業員のことを考えて経営すると株価上がるのか」と、腹落ちしたようです(笑)。

